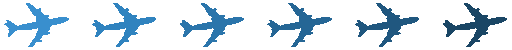私の方は、そんな経験が乏しいものだら慌ててしまい、300mmの望遠レンズで二人をファインダー越しに追いかけるばかりで、なかなかシャッターを切ることが出来ません。それでも、何度かシャッターを切ると二人は「もういいでしょう」と云う感じで帰って来てしまいました。そして、「おじさん何処からきたの?」と聞きます。「日本からだよ」と答えると「じゅあ、私達日本の雑誌に乗るの?おじさん雑誌のカメラマンでしょ?」と聞いてきました。私の大きな望遠ズームレンズの付いたカメラを見て勘違いしたのでしょう。私はばか正直に「単なる日本人の旅行者だよ」と答えてしまいました。案の定、二人は「なんだ、つまらない」と云う様な表情をみせて、「じゃ、私達あっちに行くから」と云って、ローラースケート仲間が集まっている処に行ってしまいました。
2002年のロシア
2002年5月6日
その仲間達に「へんなおじさんに捕まっちゃてね〜〜」などと話しているのが聞こえてきそうな気もしましたが、でも、その彼女達は、今のすさまじい日本の女子高生とは、やはりどこか違う感じがして、日本の女の子の様にならなければ良いがと云う気持ちが沸いてくる私でした。
今回、旧ソビエト連邦の崩壊から11年経ったロシアを訪れた訳ですが、その間、どれほどの変化が有ったのか、それとも、まだまだ変革中なのか、日本人旅行者の私には想像出きる範囲のものでは有りません。ただ、一瞬の出来事では有りましたが、今のロシアの若者気質みたいなものに触れ合う機会が数回有りました。その中で、一番印象に残っているのはゴーリキー公園で出会った女子高生の二人です。
エカテリーナ宮殿にて
エルミタージュ美術館にて
モスクワの街角
エピローグ
私達が、その公園のベンチで休んでいると、近くのベンチにスタイルの良い女の子が二人やって来て、ローラースケートの準備を始めました。余りにも新鮮な容姿に魅せられて、私は躊躇なく近寄って行って、「写真を撮らしてくれないか?」と尋ねました。一瞬怪訝な表情を見せましたが、二人とも直ぐににっこりして「いいわよ、私達どうすればいい?」と聞き返してきました。私は「ローラースケートをしているところを、少し離れた処から撮りたいんだ」と告げました。すると、準備の出来た二人は、目の前の広場に飛び出して行き、恥ずかしそうだけど、しっかりカメラを意識している様で、その辺りをゆっくりと走り回ってくれました。
モスクワ中心街にあるゴーリキー公園にて
そしてアメリカからの一方的な情報の氾濫の中で生活しているにもかかわらず、大人達は何の不安もなさそうに経済大国日本を推し進めていました。少年の私には、そんな日本の社会は間違っていないのか?と云う疑問が少しづつ広がっていました。廻りの大人に尋ねても私の疑問に明確な解答は有りませんでした。時にふれ、テレビにはあの「赤の広場」や「クレムリン」や「天安門広場」の姿を映し出しますが、決してそれ以上の情報を提供してくれる事は有りませんでした。凡人の私には、そんな疑問を消し去る事も出来ないまま、ぐずぐずと時を過ごし、そして、恥ずかしながら人並みに社会人になってしまいました。
今回、私達が訪れたロシアの都市は、モスクワとサンクトペテルブルグの2ヶ所だけです。この広大な国家の2都市だけを訪れただけでは、到底ロシアを理解したなどと言える訳が有りませんが、私の中では、随分と以前からくすぶっていたもやもやを、少し取り払う事が出来たような気がします。
そうこうする内に、1991年の旧ソビエト連邦の崩壊を迎えてしまいました。その時私は何かしらの安堵感を覚えたものです。この安堵感は、多分、少年の頃から引きずって来た足かせみたいな物が爆発して、何処かに消え去ってしまった様に感じるところから来ていたのでしょう。そしてその安堵感から、私のロシア訪問意欲の順番は他の国と比べて、だんだんと後回しになっていました。
今思えば、その旅行が私の人生を方向づけた気がします。その中国旅行で社会主義国家の状況をほんの少し垣間見ただけですが、その時すでに日本社会にどっぷりと首まで浸かっていた私には、もう方向転換などしたくないと思う程の多くの光景に出会いました。今ここで、その時の感動を書き表す積もりは有りません。別の機会を作らねばと思っています。ただ、少年時代から持ち続けた疑問の一片を切り崩したと云う気持ちにはなれました。そして次ぎは、早い内にソビエト(当時)を訪れなければ!と云う気持ちが沸いていました。しかし、凡人は幾つになっても凡人のままなのでしょう、中国を見た!と云う安心感も有りましたが、実際は、日々の仕事に追われて、何時しかその希望も希薄なものとなっていました。
社会人として目まぐるしい生活をしている33歳の時、あるチャンスが有りました。下関市と中国の青島(チンタオ)市の姉妹都市締結1周年を記念して、青島、天津、北京に政治がらみの大訪問団を派遣すると言う行事でした。地元の建設会社に勤めている私は、業界団体の斡旋も有り、また、県知事や市長や議員さん達も多数参加すると聞いて千載一遇のチャンスと思って参加しました。
前にも書いた様に、「赤の広場」と「クレムリン」は私の少年時代からの悩みの種だった訳ですが、その意味はこうです。私が10歳の時(昭和32年)我が家にテレビが購入されました。誰もがそうであった様に私もテレビの虜となり、親に叱られても叱られてもテレビに噛り付いたものです。その中にはアメリカの番組が随分有りました。そして知らず知らずの内に私達はアメリカナイズされた日本社会の中で成長していった訳ですが、中学生から高校生になった頃には、世界にはアメリカや日本と社会体制がまったく違う国が沢山在る事を知ります。さらに冷戦なるものが存在し世界は東西が対峙している事を知りました。