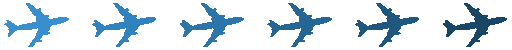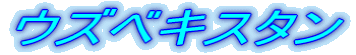カラーン・ミナレットとカラーン・モスク
4日目はブハラに滞在で、盛り沢山の一日でした。最初はブハラのシンボル、カラーン・ミナレットがあるカラーン・モスクです。 |
|
|
|
カラーン・モスク
カラーン・モスクの中庭です。サマルカンドのビビハニム・モスクに匹敵するほど広大なモスクで1万人の信者が一度に礼拝出来るそうです。 |
カラーン・ミナレット
1127年にカラハーン朝のアルスラン・ハーンによって建てられたもので、高さは46mもあります。塔は上に行くにしたがって細くなる円筒形で、塔身の壁面を14層の帯状に分け、それぞれレンガを異なる積み方で装飾しています。 |
|
|
|
灯火用窓の下の1層だけに青いタイルが使用されています。 |
| かのチンギス・ハーンはここブハラにもやって来たが、このカラーン・ミナレットだけは破壊することなく残されました。 |
|
|
|
タキ・ザルガラン
カラーン・モスクの直ぐ近くです。タキとは大通りの交差点を丸屋根で覆ったバザールで、昔は関所の役割もあったそうです。一番大きな丸屋根が交差点の中心で、周りには、商店や職人の仕事場があり、さらに、キャラバンサライやハンマム(トルコ式岩風呂)がシルクロードが栄えた時代からあるようです。 |
| タキ・ザルガランの中は、もちろん現在でもバザールです。 |
|
|
|
ブハラのウルグベク・メドレセ
ティムールの孫ウルグベクが、真の教育施設にしたいと願って1418年に建てた、現存する中央アジアで最古の神学校です。サマルカンドのレギスタン広場のウルグベク・メドレセより2年早い創建です。入口に「知識はすべてのムスリム男女の務め」「アッラーを信じる者は常に神の祝福を受ける」と云う碑文が書かれているそうです。 |
アブドゥールアジス・ハーン・メドレセ
通りを挟んでウルグベク・メドレセの向かい側にあります・1600年頃建てられたそうですが、現在はバザールになっています。中庭には絨毯が広げられていました。
|
|
|
|
バザールのおじさん。非常に愛想が良くて、民謡を披露してくれました。 |
| 同じくバザールの一角ですが、こちらのおじさん達は、観光客に見向きもしないでゲームに集中していました。 |
|
|
|
ラビ・ハウズ
お昼ご飯を食べたレストラン前です。ハウズとは池のこと。シルクロードのオアシス都市のなかでも、特に水の豊かなブハラの町には200近くのハウズがあったそうですが、不衛生で疫病が流行ったため現在では6つのハウズが残るのみです。この池の周りで男達はお茶をするわけです。 |
アルク城
古代ブハラの発祥の地ですが、やはりチンギス・ハーンに破壊されました。その後造り直され、1920年にロシア軍に攻略され滅亡するまで、歴代ハーンの居城となっていました。 |
|
|
|
城門の前は、やはり、レギスタン広場と云います。ドイツ辺りのマルクト広場みたいなものでしょう。セントラルパークですね。この広場で歴代のハーンに反抗した人達が処刑されています。 |
チャシュマ・アイユブ
チャシュマは”泉”、アイユブは旧約聖書に出てくる予言者ヨブのことで、”ヨブの泉”と云う名前です。人々が水不足で苦しんでいたとき、ヨブがここを杖で叩いたら、泉が湧き出たと云う伝説によるそうです。今でも中に泉があり、水がこんこんと湧き出しています。 |
|
|
|
イスマイール・サーマーニ廟
世界中の考古学者や建築家に注目されている、イスラーム初期の建築様式の霊廟です。892年から943年にかけて造られた中央アジアに現存する最古のイスラーム建築です。大きさは9m四方で、壁の厚さ1.8m。日干しレンガを積み上げ、半球ドーム型の屋根の単純な構造ですが、外壁は垂直ではなく、内転びにしてあります。そして、さまざまな形式のレンガの積み方で外壁の模様を表現しています。 |
ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ
4日目最後の訪問は夕食のレストランです。レストランと云っても1622年に建てられたナディール・ディヴァンベギ・メドレセと云う立派な神学校です。このメドレセの入口アーチにもイスラーム教義に反して、人の顔が描かれた太陽に向かって飛ぶ2羽の鳳凰(白いシカをつかんでいる)が描かれています。このメドレセの中庭を使って民族舞踊のディナーショーが行われました。どういう訳だか、近代的なファッションショーもありました。 |
|